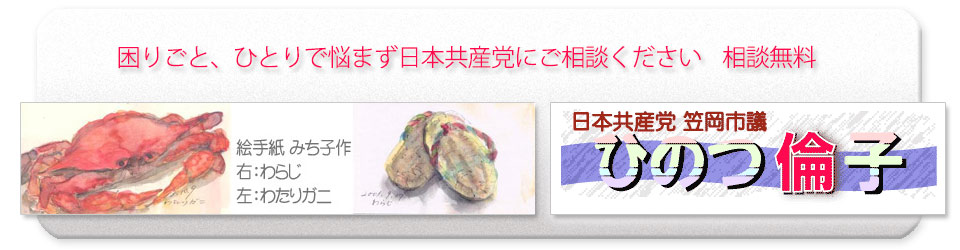本町の東に雨天時に必ず排水の悪さを感じさせるところがあります。先日改善をお願いしましたが、その2件となりも同様でした。こんな天気には歩きたくない、出たくない気分にさせられますが、ますます助長するような現象何とかなりませんか?すでに環境課から建設課の方に話が回っていますが、追加でまた連絡してみていただくようお願いしました。
「あしあと」カテゴリーアーカイブ
これは便利!
カラスのいたずら
車が不具合で持ち帰って直してもらっています。勢い今日の活動は自転車になりました。私にはちょうどこれでいいのです。西本町を通りかかったら、橋の上のごみ収集ネットがめくれていて、カラスがつついていました。私が自転車を止めて降りようとすると、近くの電信柱に、カメラを構えるとまたその向こうの電信柱に移動します。なんと計算しているのでしょうか?ここなら安全という距離を測っているのかも知れません。横浜の友人がごみ置き場のカラスを追い払ったら、次の週、攻撃されたと言いますから侮れません。仕事帰りに環境課にお願いし大きな袋状のネットにかえてもらいました。これでしばらく様子を見ます。
太刀魚
生活改善≒減量?
まちづくり講演会
今日Do!この指とまれ とタイトルが付け加えられた講演会が16日グランドホテルで行われました。講師は福山大学の前山教授でした。テーマは、「日本と世界における協同のまちづくりの最先端」でしたので、始まったばかりの笠岡には重いかな?と思いつつ聞きました。お話の導入部分には感心させられました。なぜ協働のまちづくりなのか、というお話に、今の日本の社会に薄れつつある絆を危機と捉え、笠岡らしい絆を構築する上でも必要だと説かれました。データも、OECD調査で、「困っている人の手助け」にかかわって、日本は、最も低く、「困っていても何もしない国民」ととらえられていること、深い付き合い・頼る人は?と聞かれて1位職場の同僚2位親戚3位地域4位家族だったのが、2008年では家族がダントツトップに躍り出たと報告され、「他に頼るところないというある意味刹那的な現象」と分析された。加えて少子高齢化の社会現象のもと、縮小される社会だからこそ、コミュニティ自治を作り上げようというわけだ。「若い世代も大切だが60代70代の団塊世代をどう社会の力に生かすのか」が大切だという。先進例のアメリカシアトル「ヒルサイドガーデン」プロジェクトは、行政が1万㌦出し、地元市民が対価の労働力を出してゴミ捨て場を菜園に変えていくという話、高知市でのコミュニティ計画では地区毎に振興計画をつくり、地域設計を市民の手で立てるという構図だ。構想も、概念も進むべき方向としては本当に素晴らしいと思いました。しかし現実はそうはいきません。地元やいくつかの今の協議会のあり方を振り返ってみると、たとえば神島の保育所問題の様に、住民の声が十分汲み上げられていない点や、「『お上』行政を克服するために市民の手で」といううたい文句にも関わらず、保守的な地域性のもとで、やはり地域の『お上』行政になっているという点もあったりと、笠岡市は真の自治のあり方が問われているように思えます。声なき声に心を寄せ、少数意見を生かし、地区全体の納得に結び付けていく民主的手法と人間性が求められているのではないでしょうか。最後に司会の協働のまちづくり課井上課長は、「前山先生に講演の依頼をしに行った時、『協働』とはどういう意味かと聞きました。すると先生は『バラバラになっているものをまとめて動くようにすることだ』とこたえられ、それが今日の話の中の『きずな』だと思いました。」と導入部分がすべてを物語っていることにふれ、とてもスマートに会を締めくくりました。私は発言できなかったこうしたいくつかの質問を直接先生に伺ってみようと思いました。
県民局で要望
生き生きサロン
壁掛け展示
目見張る展示工夫
シークレットを初め、森信学芸員の説明にも目を見張りましたが、展示の工夫もあっと驚かされます。透明のキャップに覆われて、光をめぐらせたドーム型、そのドームを陳列の上にはめ込み、ブルーに点灯されたコーナーを覗き込むとまるで潜水艦から海を眺めているような気持ちになる臨場型、廃物を利用してのバードハウスや、棚展示には制作者浅野さんの知恵がいっぱいでした。